はじめに

こんにちは!ADHDのマイマイです。
皆さんはこんなことで悩んだことはありませんか?
もしかしたらそれらはADHD(注意欠如・多動症)の症状かもしれません。
今回はADHDの診断を受けた私マイマイが、当事者としての体験と知識を交えながら詳しくお話ししていこうと思います。
簡単な自己紹介・病歴
まずは、ADHD当事者である私の自己紹介をさせていただきます。
私は中学2年生の頃から不登校になり、その後、通信制高校へ入学しました。
しかし課題のレポート提出に強い苦手意識を感じ、入学からわずか半年で自主退学。
2025年6月、18歳となり、成人を機に一人暮らしを始めて経済的に独立しました。
長年感じていた生きづらさや集中の問題などを相談するため、メンタルクリニックを受診。
そして同年9月に、ADHD(注意欠如・多動症)の診断を受けました。
小学生の頃から「理解はできているのにミスが多い」タイプで、
100点分の内容を理解していても、いつも80点くらいの結果になってしまうような子どもでした。
いつも何か別のことを考えていたり、授業中に落ち着かなかったりと、
周囲から「集中して」と言われることも多かったです。
ミスが多く、父からは幼き頃「病的だね」と言われていたことを思い出し、壮大な伏線だったのだと感心しました。笑

他人から見たら相当挙動がおかしくみえていたんだな!
中学に入ると、身体の多動は落ち着いたものの、頭の中は常にフル回転。
退屈な授業に強い苦痛を感じ、次第に学校へ行けなくなっていきました。
通信制高校に進学してからも、課題への取り組みに強い忌避感を覚えるようになり、
課題を目にするだけで、難易度は簡単にもかかわらず、まるで脳がシャットダウンしたのような感覚を感じるようになっていました。
「提出しなければ」と思っても体が動かず、最終的に退学を選びました。
その後は約1年間の引きこもり期間を経て、今は少しずつ社会と関わりながら働いています。
誰でも詳しくわかる!ADHDのこと
※ここからの内容は、当事者である私自身の経験と知識をもとに書いたものであり、専門的な内容ではありません。
できる限り誤解を招かないよう注意し、正しい認識をお伝えできるよう努めておりますが、必ずしも正確な情報であるとは限りません。
ここからは、できるだけわかりやすく噛み砕いて、ADHDとはどういった障害なのかを説明していこうと思います。
まず大前提として、ADHD(注意欠如・多動症)はその名の通り、「注意が続きにくい」「落ち着きがない・衝動的に行動してしまう」といった特徴がみられる発達障害です。
人によって、注意の問題が強いタイプ、多動・衝動が強いタイプ、その両方があるタイプなど、現れ方はさまざまです。
そして、発達障害とは脳の働き方や発達に偏りがあり、その影響で行動や認知に偏りがみられる先天的な障害のことを指します。
ADHDのほかにも、ASD(自閉スペクトラム症)やLD(学習障害)などが含まれます。
ここで重要なのは、発達障害は主に生まれつきの脳の特性によるものであり、「育て方」や「本人の努力不足」が原因ではないという点です。
環境が症状の出方に影響することはありますが、根本的な要因は脳の働きそのものにあります。
ADHDをはじめとする発達障害は、薬や支援によって症状を和らげることはできますが、根本的に「治す」ことはできません。
視覚化するために身体的な障害に例えるなら、先天的に脚が発達しなかった人は義足を履きますが、脚が再生して生えてくることはありませんよね?
そのような理解が、わかりやすいと思います。

- 発達障害は育て方で防げる!!
- 生活リズムが悪いから発達障害になる!!
- 発達障害にならない食べ物!!

↑こういう嘘に騙されないように注意してね!
「発達障害かも?」と思ったら、、、
これまでの内容に「当てはまることが多い」「日常生活でずっと苦労している」と感じた方は、もしかすると発達障害の可能性があります。
私自身も、小学生の頃から“生きづらさ”を強く感じていました。
中学生のとき、思い切って父に「発達障害かもしれない」と打ち明けたこともあります。
ですが、私はWAIS(ウェイス)という知能検査で IQ115(上位約15%) を出せるほど、特定の分野以外の知的能力は高いほうでした。
そのため父からは、
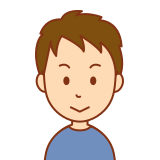
思い過ごしじゃない?あなたが障害者だとは思えないよ
といった反応でした。
自分の頑張りがたりないのか?、、、
こういった不安でなかなか寝付けないこともありました。
しかし、成人してから親に知らせずメンタルクリニックを受診したところ、なんと2回目の診察で正式にADHDの診断が下りました。
発達障害は、特定の分野だけ極端に苦手がある一方で、他の分野ではむしろ優れているというケースが多く見られます。
私の場合もまさにそうで、WAISの結果からそれがはっきりと分かりました。
私のWAISの結果
- 言語理解 :IQ113
- 知覚推理 :IQ116
- ワーキングメモリ :IQ106
- 処理速度 :IQ82
- 全検査 :IQ108
この結果から、言語理解や知覚推理(いわゆる“頭の良さ”)は平均よりかなり高い一方で、
処理速度(集中力・正確さ)は大きく平均を下回っている、という脳のバランスの偏りが見えてきました。
WAISは、こうした自分の脳の得意・不得意の傾向を具体的に知ることができる、とても有用な心理検査です。
受けるには、まずかかりつけのメンタルクリニックや精神科・心療内科で「WAISを受けられますか?」と問い合わせてみてください。
もし今、「自分も発達障害かもしれない」と感じている方は、ぜひ一度専門医に相談してみてください。
治療薬ってどんなものがあるの?
ADHDの治療には、大きく分けて 「刺激薬」 と 「非刺激薬」 の2種類があります。
どちらも脳の中で情報をやり取りしている「神経伝達物質」という物質の働きを整える薬です。
薬によって、脳の“通信”がスムーズになり、注意力や集中力が続きやすくなるようサポートしてくれます。
非刺激薬(ストラテラ・インチュニブなど)
代表的な薬:ストラテラ(アトモキセチン)、インチュニブ(グアンファシン)
このタイプの薬は、ノルアドレナリンという物質のやり取りを改善するはたらきがあります。
ノルアドレナリンは、
「行動を起こす」「やる気を出す」「集中を維持する」
といったときに大切な役割を持つ神経伝達物質です。
ADHDの人はこのノルアドレナリンの動きが弱かったり、すぐに途切れてしまったりすることがあり、
結果として「集中が続かない」「やる気が出ない」といった状態が起こります。
アトモキセチン(ストラテラ)などの薬は、そのノルアドレナリンの“受け渡し”をスムーズにすることで、
気持ちが落ち着いたり、行動を起こしやすくなったりする効果が期待できます。
ただし、効果が出るまで数週間〜数か月かかることがあり、
「少しずつ効いてくるタイプ」の薬です。
刺激薬(コンサータ・ビバンセなど)
代表的な薬:コンサータ(メチルフェニデート)、ビバンセ(リスデキサンフェタミン)
このタイプは、脳内の ドーパミン と ノルアドレナリン の働きを活発にして、
「注意を向ける」「思考を整理する」といった力を一時的に高める薬です。
ドーパミンは「達成感」や「快感」に関係する物質で、
これが不足すると「やる気スイッチ」が入りづらくなります。
刺激薬では、このドーパミンやノルアドレナリンの働きを一時的に高めることで、
「頭の中が静かになる」「タスクに集中できる」「考えがまとまりやすくなる」
といった変化が見られることがあります。
効果の現れが比較的早く、服用後すぐに集中しやすくなる方も多いです。
一方で、不眠や食欲低下などの副作用が出ることがあり、医師の慎重な管理が必要です。
薬は“能力を上げる”ものではない
どちらの薬も、「新しい能力を与える」ものではありません。
本来その人が持っている力を発揮しやすく整えるためのサポート薬です。
服用によって「集中が続くようになった」「頭の中のごちゃごちゃが減った」と感じる方が多いですが、
一方で合う・合わないは人それぞれです。
医師と相談しながら、少しずつ自分に合った方法を見つけていくことが大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、ADHD当事者である私自身の経験をもとに、ADHDや発達障害についてお話ししてみました。
この記事が、少しでも皆さんの理解を深めるきっかけになったり、
「自分もそうかもしれない」と感じた方の気づきにつながれば嬉しく思います。
もし、発達障害やADHDのことで気になること・悩んでいることがありましたら、
お気軽にお問い合わせにお寄せください。
できる限り、気づき次第お返事させていただきます。
そして、このブログが「参考になった」「読んでよかった」と感じていただけたら、
ぜひSNSなどでシェア・紹介していただけると励みになります。
皆さまからのコメントや感想も、心よりお待ちしております。
ADHDに関する詳しいレポート
また、まだまだ詳しく、そして正確性の高いソースで情報を得たい方向けにレポートをつくりましたので、良ければぜひ見てみてください。







コメント